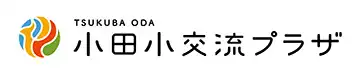小田祇園祭で東部のお神輿に対峙する、中部側の主役「大獅子」とお囃子を受け継いでいる、「小田大獅子保存会」による祭りの準備を取材しました。
大獅子製作の技
祇園祭まであと2週間を切った休日の昼間、田向延寿院の境内で大獅子の製作が進んでいました。
大獅子は毎年、竹の切り出しからはじめ、獅子頭以外は全て作り直しています。
それがもう既に、10mほどもある巨大な竹の骨格が組み上がっていました。
「今年は雨が少なかったからね。」とおっしゃいますが、炎天下の作業は過酷だったことでしょう。
担ぐとき手が触れる所は全て、竹でケガをしないように荒縄を巻くそうです。
そこでは「男結び」と言われる、竹垣などに使う解けない方法で荒縄を結んでいます。
ゆっくり結んで教えてくださるのですが、これには今回初めて製作に参加した方も四苦八苦。
「結果は同じなんだけど、人によってやり方がちょっと違うんだよね。」と、みなさんそれぞれに自分なりのやり方を試行錯誤して見つけているようです。
また荒縄を繋ぐときには、両方の縄をきつく撚り合わせていました。
このやり方で、顔合わせで荒っぽく競ったあとでもほぼ修復の必要がない、とのことです。
ここにも熟達した技がありました。
子どもたちと小田祇園祭
平日仕事と夕食が終わる20時頃からは、同じ延寿院の境内にてお囃子の練習が始まります。
この日も親と一緒に来た保育所の年長さんから、小さい頃親に連れてこられた中高生、そして大人たちが練習に参加していました。
子どもが親と太鼓をたたき始めると、周りの人もたたき、それを見た子どもがリズムや叩き方を真似している様子が見られました。
「はじめて叩いたの?」と訊くと、「保育所でもやってる!」とのこと。
中高生も大人についてもらい、時には調子を合わせてもらい、演奏をすすめていました。
まちをあげて祭りに取り組んでいることが分かります。
クライマックスである「顔合わせ」の直後、保存会では「散切(さんぎり)」という特別な調べを大太鼓のソロでたたきます。
このときには祭りの賑やかな空気が一転して鎮まり始め、凛とした力強い音色に辺りが包まれます。
自分で太鼓をたたき始めると、複雑な調子をかっこよく叩ける大人に憧れるでしょう。
小田ではこんな風に、子どもたちが祭りに入っていくんだなあ、と思いました。
祭り当日の予定
小田大獅子保存会は、祭り当日の早朝から大獅子の装飾など最後の仕上げを行います。
そのあと8時頃から町内を囃し立てながら、縁起物の「神藻(もく)」を配ります。
これは大獅子の髪にも使われている、「ササバモ」という水草を乾燥させたものです。
20時頃から大獅子を引き、お神輿との顔合わせに向かいます。
散切太鼓のあと、参睦一据(サンボクイッセイ)で締めると、大獅子は延寿院に戻ります。
ここでも大獅子を上げたり、お囃子を奏でることがあるそうです。
ぜひ生の小田祇園祭を堪能しに、お越しくださいませ。
小田大獅子保存会の活動
小田祇園祭のあと、保存会では小田西部の天神万灯のほか、隣町の北条の祇園祭などにも支援に向かうそうです。
「代わりに向こうからも、小田の手伝いに来てくれるんです。」
地域の祭りはそのように助け合いながら、紡がれています。
元々大獅子は祇園祭が終わるとすぐ解体していました。
でも今年は、2025年8月25日(土)のまつりつくばのパレードに、大獅子も参加するそうです。
巨大で勇猛な大獅子が宙を舞う姿を、まつりつくばでぜひご覧ください。
より詳しい情報が得られる、小田大獅子保存会のホームページとSNSには、下記ボタンから入れます。
小田大獅子保存会には、小田地区の内外問わず入会して活動に参加できるそうです。
記者・写真撮影:めーさん、動画撮影:TKCツーリング